2011年7月
31件の記事があります。
2011年07月07日見ておきたいですね
秋田 足利 直哉
巡視からの帰り道、とある神社の祭典が行われていていつも通る道路が通行止めに・・・。思わぬ遠回りをしましたが、そこが渋滞で・・・。でもまぁお祭りですからね~^^。仕事がなければそのお祭りを見てみたかったです。
最近、窓の外からは竿灯のお囃子が聞こえてきます。これから東北は夏祭りの季節を迎えます。楽しみになってきました!!
はい。楽しみと言えば・・・『毎年来るのを楽しみにしている』野鳥っていますよね?あの鳥に会っておかないとなんか落ち着かないというか・・物足りないというか・・・。今日はそんな野鳥の話題です。
この時期、周囲の”緑”がどんどん色濃くなり空の青さも増してきていますよね?そんな中、『白』が目を引きます。特に『シラサギ』と呼ばれる全身真っ白のサギ達は田んぼにいても、ヨシの中にいても、水辺にいてもその場所と白い羽のコントラストが美しく目を惹かれてしまいます。
コロニーではダイサギがそろそろ巣立ちの時を迎えそうです。保護区内の水辺では親鳥が採餌する様子を見かけます。ダイサギは「静」!自分の位置を決めたらそこに餌がくるまでで「待つ」というスタイルのようです。
最近田んぼを中心に姿を現すようになったチュウサギは、「動」!動き回って「積極的に餌を探す」というスタイル。同じく田んぼや休耕田で見かけるコサギは「技」!歩きながらも自分の脚を左右に振って餌を「誘き出して捕まえる」スタイル。この様に一口に「シラサギ」と言ってもその食事スタイルにはそれぞれ特徴があります。
そんな「シラサギ」の中でも最も特徴的な餌の取り方をする(と言っても過言ではないはず・・)サギを観察してきました。


水辺を動き回って餌を探すのですが・・・餌となる獲物を見つけると首を斜めに伸ばして(上の写真を参照)狙いを定めたり、体制を低くして羽を半開きにして(下の写真を参照)獲物を捕まえやすいようにしたりと、とにかく特徴的な動きをします。
このサギの名は【カラシラサギ】。これで4年連続の確認となりました。今やすっかり夏の初め恒例のお客様となりました。今年の夏は『○○にも【カラシラサギ】にも逢えたし・・』と幸先がイイです!!
最近、窓の外からは竿灯のお囃子が聞こえてきます。これから東北は夏祭りの季節を迎えます。楽しみになってきました!!
はい。楽しみと言えば・・・『毎年来るのを楽しみにしている』野鳥っていますよね?あの鳥に会っておかないとなんか落ち着かないというか・・物足りないというか・・・。今日はそんな野鳥の話題です。
この時期、周囲の”緑”がどんどん色濃くなり空の青さも増してきていますよね?そんな中、『白』が目を引きます。特に『シラサギ』と呼ばれる全身真っ白のサギ達は田んぼにいても、ヨシの中にいても、水辺にいてもその場所と白い羽のコントラストが美しく目を惹かれてしまいます。
コロニーではダイサギがそろそろ巣立ちの時を迎えそうです。保護区内の水辺では親鳥が採餌する様子を見かけます。ダイサギは「静」!自分の位置を決めたらそこに餌がくるまでで「待つ」というスタイルのようです。
最近田んぼを中心に姿を現すようになったチュウサギは、「動」!動き回って「積極的に餌を探す」というスタイル。同じく田んぼや休耕田で見かけるコサギは「技」!歩きながらも自分の脚を左右に振って餌を「誘き出して捕まえる」スタイル。この様に一口に「シラサギ」と言ってもその食事スタイルにはそれぞれ特徴があります。
そんな「シラサギ」の中でも最も特徴的な餌の取り方をする(と言っても過言ではないはず・・)サギを観察してきました。


水辺を動き回って餌を探すのですが・・・餌となる獲物を見つけると首を斜めに伸ばして(上の写真を参照)狙いを定めたり、体制を低くして羽を半開きにして(下の写真を参照)獲物を捕まえやすいようにしたりと、とにかく特徴的な動きをします。
このサギの名は【カラシラサギ】。これで4年連続の確認となりました。今やすっかり夏の初め恒例のお客様となりました。今年の夏は『○○にも【カラシラサギ】にも逢えたし・・』と幸先がイイです!!
2011年07月06日救命講習を受講しました
秋田 足利 直哉
今日、当事務所でも入口に掲示している黄色い「節電中」の張り紙を2回見ました。事務所のあるビルの中でも挨拶と共にする会話が『今年はまだエアコン付けてませんよ』とか『そちらの事務所(当事務所)はいつも照明無しですね?』なんていう話題になっています。
はい。今日は珍しく(?)自然情報ではない話題を取り上げました。正直な話、『こんな話を書いてもつまんないよな~』と巡視や調査以外の日常の業務についての話題を避けていました。しかしながら・・・森吉山野生鳥獣センターを訪れる方の安心に繋がれば幸いと思い、この話題を取り上げました。
先日、北秋田市消防本部に依頼しまして、森吉山野生鳥獣センターまで出張していただき、森吉山野生鳥獣センター案内解説員、清掃員、秋田自然保護官事務所スタッフなどで普通救命講習+αを受講しました。
森吉山野生鳥獣センターにはAEDを設置しています。これは国道285号線を離れて奥森吉と呼ばれるエリアに至るまでで唯一のAEDなんだそうです。ちなみに森吉山周辺では阿仁スキー場に設置してあるそうです。いずれにしてもかなり貴重な機器であることに間違いありません。その機器をいざという時、適正に活用できなければ意味がありません。なので森吉山野生鳥獣センターの関係者には身につけておかなければならない知識・経験です。

先ずはスライドを見て講習の”ねらい”や概要を理解します。
次いで救急救命士の方の見本を見ながら過去に受けた講習の記憶を呼び覚まします。私自身ももう何度も普通救命講習を受講していますし、受講者全員がこれまでに同様の講習を受けていましたが、ここを疎かにするわけにはいきません!!心肺蘇生法しかり!AEDの使い方しかり!!
そして受講者全員で心肺蘇生法のトレーニングです。効率的な身体の使い方と心臓マッサージの『1分間に100回のペース』が主なテーマです。
森吉山野生鳥獣センターではAEDの設置以降、これを使うような事例は起きていませんが、遭難事故は毎年複数件起きているのが実情です。「道迷い」が多いようですが中には転倒や滑落事故も起きています。そうした実情に対応するため、特別にお願いして森吉山野生鳥獣センター周辺で想定される事故に対処する為の方法も教えていただきました。

遭難者を安全な場所や処置可能な場所へ移動させる為の方法。骨折や打撲、捻挫した時、患部を固定する方法。裂傷による出血を止める方法を教えていただきました。
また野外ではしっかりした道具や装備が無い場合も考えられますので、身の回りの物や登山の装備を使って担架を作る方法等も教えていただきました。
遭難者を担ぐ時、ちょっとした”持ち方”の違いで随分と効率が違うものです。そして普段から多少の装備を持って歩いてはいますが、それで万全ではありません。今回教えていただいた登山道具や衣服などを使う方法を是非とも自主研修などをして身につけたいと思います。
今回の研修が役に立つ場面が無いのがベストです。救急救命士の方もおっしゃっていましたが『先ずは予防』から!!しかし思わぬ落とし穴に陥って事故に繋がる事も考えられます。そうした事態に対応するための心構えを一段とレベルアップできた講習会でした。
はい。今日は珍しく(?)自然情報ではない話題を取り上げました。正直な話、『こんな話を書いてもつまんないよな~』と巡視や調査以外の日常の業務についての話題を避けていました。しかしながら・・・森吉山野生鳥獣センターを訪れる方の安心に繋がれば幸いと思い、この話題を取り上げました。
先日、北秋田市消防本部に依頼しまして、森吉山野生鳥獣センターまで出張していただき、森吉山野生鳥獣センター案内解説員、清掃員、秋田自然保護官事務所スタッフなどで普通救命講習+αを受講しました。
森吉山野生鳥獣センターにはAEDを設置しています。これは国道285号線を離れて奥森吉と呼ばれるエリアに至るまでで唯一のAEDなんだそうです。ちなみに森吉山周辺では阿仁スキー場に設置してあるそうです。いずれにしてもかなり貴重な機器であることに間違いありません。その機器をいざという時、適正に活用できなければ意味がありません。なので森吉山野生鳥獣センターの関係者には身につけておかなければならない知識・経験です。

先ずはスライドを見て講習の”ねらい”や概要を理解します。
次いで救急救命士の方の見本を見ながら過去に受けた講習の記憶を呼び覚まします。私自身ももう何度も普通救命講習を受講していますし、受講者全員がこれまでに同様の講習を受けていましたが、ここを疎かにするわけにはいきません!!心肺蘇生法しかり!AEDの使い方しかり!!
そして受講者全員で心肺蘇生法のトレーニングです。効率的な身体の使い方と心臓マッサージの『1分間に100回のペース』が主なテーマです。
森吉山野生鳥獣センターではAEDの設置以降、これを使うような事例は起きていませんが、遭難事故は毎年複数件起きているのが実情です。「道迷い」が多いようですが中には転倒や滑落事故も起きています。そうした実情に対応するため、特別にお願いして森吉山野生鳥獣センター周辺で想定される事故に対処する為の方法も教えていただきました。

遭難者を安全な場所や処置可能な場所へ移動させる為の方法。骨折や打撲、捻挫した時、患部を固定する方法。裂傷による出血を止める方法を教えていただきました。
また野外ではしっかりした道具や装備が無い場合も考えられますので、身の回りの物や登山の装備を使って担架を作る方法等も教えていただきました。
遭難者を担ぐ時、ちょっとした”持ち方”の違いで随分と効率が違うものです。そして普段から多少の装備を持って歩いてはいますが、それで万全ではありません。今回教えていただいた登山道具や衣服などを使う方法を是非とも自主研修などをして身につけたいと思います。
今回の研修が役に立つ場面が無いのがベストです。救急救命士の方もおっしゃっていましたが『先ずは予防』から!!しかし思わぬ落とし穴に陥って事故に繋がる事も考えられます。そうした事態に対応するための心構えを一段とレベルアップできた講習会でした。
2011年07月06日今年は当たり年?
磐梯朝日国立公園 裏磐梯 星 彰
裏磐梯は、梅雨らしい天気が続いています。週間天気予報を見ても、曇りや傘マークばかりで、ついため息が出てしまいそうです…。気分も落ち込みがちな季節ですが、先日(6月30日)ニッコウキスゲが見頃を迎えた雄国沼へ行ってみました。今年も湿原に見事な黄色絨毯が広がり、たくさんの来訪者で賑わっていました。
今回は、前回の記事に引き続いてしまいますが、ニッコウキスゲが見頃となっている雄国沼をご紹介したいと思います。

ニッコウキスゲ(6/30)

木道は昨年の秋に付け換えられ、幅が広くなりました。
立ち止まっても、道を塞ぐことは無くなったので、のんびりと観賞できます。
雄国沼監視員の方の話では、昨年に比べ1.5倍くらいニッコウキスゲは多いとか…。

コバイケイソウの花も群落までは行きませんが、花の数は多い印象を受けます。

こちらは、サワラン。ピンク色の花が目を引きますが、湿原にはまばらにしか咲いていません。
この他、ヒオウギアヤメ、レンゲツツジ、ワタスゲ(果穂)も確認できました。
開花のピークもそろそろ終盤を迎えつつありますので、行かれる方はお早めに。
また、前回の記事にも書きましたが、7月18日(月・祝)まで、雄国沼ではマイカー規制が行われています。雄国萩平駐車場~金澤峠まではシャトルバスが運行されていますので、喜多方市側から行かれる方はシャトルバスをご利用ください。北塩原村側の雄子沢登山口からは、1時間ほどで行くことができますが、ニッコウキスゲが見頃となるシーズンは登山口の駐車場は大変混み合いますので、ご注意ください。
今回は、前回の記事に引き続いてしまいますが、ニッコウキスゲが見頃となっている雄国沼をご紹介したいと思います。
ニッコウキスゲ(6/30)
木道は昨年の秋に付け換えられ、幅が広くなりました。
立ち止まっても、道を塞ぐことは無くなったので、のんびりと観賞できます。
雄国沼監視員の方の話では、昨年に比べ1.5倍くらいニッコウキスゲは多いとか…。
コバイケイソウの花も群落までは行きませんが、花の数は多い印象を受けます。
こちらは、サワラン。ピンク色の花が目を引きますが、湿原にはまばらにしか咲いていません。
この他、ヒオウギアヤメ、レンゲツツジ、ワタスゲ(果穂)も確認できました。
開花のピークもそろそろ終盤を迎えつつありますので、行かれる方はお早めに。
また、前回の記事にも書きましたが、7月18日(月・祝)まで、雄国沼ではマイカー規制が行われています。雄国萩平駐車場~金澤峠まではシャトルバスが運行されていますので、喜多方市側から行かれる方はシャトルバスをご利用ください。北塩原村側の雄子沢登山口からは、1時間ほどで行くことができますが、ニッコウキスゲが見頃となるシーズンは登山口の駐車場は大変混み合いますので、ご注意ください。
2011年07月06日飯豊連峰保全連絡会 第7回会合が実施されました。
磐梯朝日国立公園 羽黒 佐々木 大樹
7月5日(火)、飯豊連峰保全連絡会の第7回会合が新潟県関川村村民会館で実施されました。
議題では任期満了に伴う幹事改選ということで、現行代表・幹事の8名継続が承認され、また中条山ノ会の亀山氏を加えた9名体制となることが承認されました。

新幹事の亀山氏から挨拶です。いつも山でもお世話になっています。
また、各団体の飯豊連峰の計画している、登山道整備、保全作業等について情報交換が行われました。
合同保全作業については、第6回会合でもお伝えしましたとおり、10月1日(土)~2日(日)に草月平周辺で実施します。
また、その他議題として、飯豊連峰保全連絡会の下部組織として、技術部会(仮)が設置されることが承認されました。
詳細については、関係者の皆様にはニュースレターをお送りしますのでよろしくお願いします。

会合の様子
議題では任期満了に伴う幹事改選ということで、現行代表・幹事の8名継続が承認され、また中条山ノ会の亀山氏を加えた9名体制となることが承認されました。

新幹事の亀山氏から挨拶です。いつも山でもお世話になっています。
また、各団体の飯豊連峰の計画している、登山道整備、保全作業等について情報交換が行われました。
合同保全作業については、第6回会合でもお伝えしましたとおり、10月1日(土)~2日(日)に草月平周辺で実施します。
また、その他議題として、飯豊連峰保全連絡会の下部組織として、技術部会(仮)が設置されることが承認されました。
詳細については、関係者の皆様にはニュースレターをお送りしますのでよろしくお願いします。

会合の様子
2011年07月06日動く砂
仙台 鎌田 和子
今日の仙台は暑いのですが、昨日までの蒸し暑さとは違い、カラッとしているように感じです。
6月下旬に仙台海浜鳥獣保護区に調査にでかけてきましたのでその時の変化をお伝えします。
蒲生干潟に出かける度に、「アッ変わっている!」とつい出てしまうのです。今回は七北田川から干潟に水が出入りする部分の導流堤が砂に埋め尽くされているのです。

昨年5月の導流堤付近の写真です。多くの人々が潮干狩りに訪れていました。

震災後、4月14日に撮影した導流堤部分です。この日は満潮に近い時間でしたので、水量たっぷりでした。

これは6月上旬、昨年の潮干狩りの写真に近い感じと思うのですが、どうでしょうか?干潟に降りるルートも流されているのですが面影がありますよね。

そして、6月下旬の状態です。たった20日間で砂が動いたのです。大潮、高潮、低気圧天候に左右される「動く砂」が海底にまだまだたっぷりあるのでしょうか?
津波で陸に砂を運んだはずなのですが、引き波で海に戻った分なのでしょうか?「動く砂」です。
今度、出かけた時にはどんな驚きが待っているのかしら?
6月下旬に仙台海浜鳥獣保護区に調査にでかけてきましたのでその時の変化をお伝えします。
蒲生干潟に出かける度に、「アッ変わっている!」とつい出てしまうのです。今回は七北田川から干潟に水が出入りする部分の導流堤が砂に埋め尽くされているのです。
昨年5月の導流堤付近の写真です。多くの人々が潮干狩りに訪れていました。
震災後、4月14日に撮影した導流堤部分です。この日は満潮に近い時間でしたので、水量たっぷりでした。
これは6月上旬、昨年の潮干狩りの写真に近い感じと思うのですが、どうでしょうか?干潟に降りるルートも流されているのですが面影がありますよね。
そして、6月下旬の状態です。たった20日間で砂が動いたのです。大潮、高潮、低気圧天候に左右される「動く砂」が海底にまだまだたっぷりあるのでしょうか?
津波で陸に砂を運んだはずなのですが、引き波で海に戻った分なのでしょうか?「動く砂」です。
今度、出かけた時にはどんな驚きが待っているのかしら?
2011年07月05日『山内小学校児童からの手紙』と『おんぶカンムリカイツブリ』
秋田 足利 直哉
先日、6月8日の日記でお伝えした、『愛鳥学習会』で大潟草原鳥獣保護区管理棟へ来てくれた横手市立山内小学校の児童達から手紙が届きました。
手紙には当日の学習会の様子や感想、その後に彼らが感じた野鳥への思いなどが書かれていました。私たちにとってこうした手紙は最高の贈り物です。

子供達の無邪気な様子を見て、一緒に過ごす時間は本当に嬉しいものです。そして今回はお礼の手紙まで貰えるなんて幸せなことです。
先日は野鳥の子供達の無邪気な様子と、親に甘える微笑ましい様子と、それを守る親の強さが感じられる観察が出来ました。
水路で繁殖活動をしている【カンムリカイツブリ】達が雛を連れて水路に姿を見せてくれるようになりました。西部承水路でも白と黒の縞々の雛達が親鳥に見守られながら過ごしています。

親鳥の背中に2羽の雛が乗っています。既に自分で泳ぐことが出来るはずですが、まだまだ小さなうちはこうして背中で過ごすことが多いようです。

こちらの写真では親鳥に寄り添うようにしてもう1羽の雛が見えます。兄弟姉妹の中でも背中で大半を過ごす雛もいれば、自力で泳ぐ雛もいるようです。でも、のっぴきならない事態が起こると全ての雛が親鳥の背中へ逃げていきました。
よく見ると親鳥も翼をやや開いて雛達が過ごしやすいようにしているようです。背中の雛が乗りやすいように!!寄り添う雛を包み込むように!!
この光景・・・この日記で過去何度かお伝えしてきています。鳥獣保護区管理員さんとも話しましたが『背中に雛を乗せたカンムリカイツブリを見ないとなんだか落ち着かないし、物足りない』んです。今や大潟草原鳥獣保護区には無くてはならない光景なのです!!そしてその光景が今年も見られたことをとても嬉しく思うのです。
手紙には当日の学習会の様子や感想、その後に彼らが感じた野鳥への思いなどが書かれていました。私たちにとってこうした手紙は最高の贈り物です。

子供達の無邪気な様子を見て、一緒に過ごす時間は本当に嬉しいものです。そして今回はお礼の手紙まで貰えるなんて幸せなことです。
先日は野鳥の子供達の無邪気な様子と、親に甘える微笑ましい様子と、それを守る親の強さが感じられる観察が出来ました。
水路で繁殖活動をしている【カンムリカイツブリ】達が雛を連れて水路に姿を見せてくれるようになりました。西部承水路でも白と黒の縞々の雛達が親鳥に見守られながら過ごしています。

親鳥の背中に2羽の雛が乗っています。既に自分で泳ぐことが出来るはずですが、まだまだ小さなうちはこうして背中で過ごすことが多いようです。

こちらの写真では親鳥に寄り添うようにしてもう1羽の雛が見えます。兄弟姉妹の中でも背中で大半を過ごす雛もいれば、自力で泳ぐ雛もいるようです。でも、のっぴきならない事態が起こると全ての雛が親鳥の背中へ逃げていきました。
よく見ると親鳥も翼をやや開いて雛達が過ごしやすいようにしているようです。背中の雛が乗りやすいように!!寄り添う雛を包み込むように!!
この光景・・・この日記で過去何度かお伝えしてきています。鳥獣保護区管理員さんとも話しましたが『背中に雛を乗せたカンムリカイツブリを見ないとなんだか落ち着かないし、物足りない』んです。今や大潟草原鳥獣保護区には無くてはならない光景なのです!!そしてその光景が今年も見られたことをとても嬉しく思うのです。
2011年07月04日『AR写真展のお知らせ』と『何度も何度も・・』
秋田 足利 直哉
現在、南秋田郡五城目町の『秋田県環境と文化のむら 自然ふれあいセンター』において『東北アクティブレンジャー写真展「心に残る風景」』を開催中です。東北各地の10名のアクティブレンジャーが自分たちの所管地の中から自分の心に残っている風景や皆様の心にきっと残るであろう風景を集めた写真展です。どうぞご覧下さい。
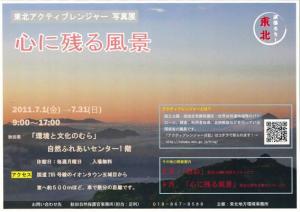
そして、森吉山野生鳥獣センターでは東北アクティブレンジャー写真展のスピンオフ企画、宮古アクティブレンジャー写真展『美しいこの光景は必ず復活します!!』を開催中です。過去3年間の宮古自然保護官事務所の高屋敷ARの写真を展示し、そこ場所の現在の情報を加えて展示してあります。
宮古を初め『被災した各地の、復興の道は果てしない』というイメージを持っている方が少なくはないようです。しかし現地では震災に影響を受けていないところもあります。例えば浄土ヶ浜VC前の駐車場から散策できる臼木山などはその一例です。また被災された皆さんが懸命に頑張って頑張って頑張って、観光客やハイカー達を迎える準備が整いつつあるところもあります。例えば浄土ヶ浜の観光船は今月16日に待望の再開を予定しているそうです。こうした現状を少しでも知っていただけたら!そして懸命に頑張っている観光地などへ足を運んで貰えるように!との思いを込めて開催しています。是非ご覧下さい。
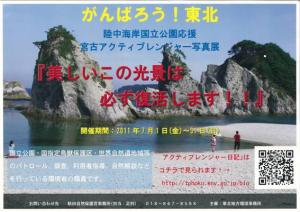
懸命に頑張っている姿というのはどうしてこんなにも心を打つのでしょうか?それは人間だけではなく先日、巡視の時に観察した【モズ】にも同じような感覚を持ちました。もしかしたら・・私は感傷的になっているかも知れません。。
森吉山麓高原内で多くの【モズ】達が繁殖中であることは以前この日記でもお伝えしました。現在はそれが佳境に入っていて、親鳥達が懸命に餌を運ぶ様子が観察できます。一日に何度運ぶのでしょうか?私が観察した時はオスもメスも入れ替わり立ち替わりで(概ね)5分と開けずに餌を運んできました。
オスの【モズ】がちょっと休憩(?)したところです。夕方になって疲労が蓄積していたのでしょうか?それとも日が暮れるまでもう一頑張りするためでしょうか?

よくみると・・・【モズ】の鮮やかなオレンジ色の羽がなりを潜め、灰色の地味な装いに替わっているではありませんか。巣のありかを周囲に悟られないようにヤブを潜って何度も何度も巣に餌を運んだからでしょうか?頭や背中部分の羽が擦り切れてきているようです。同一個体とは言い切れませんが同じ場所で数週間前に撮影した物と比べて、オレンジ色部分が無くなり灰色部分が拡大しているのが解りました。ストレッチしている時に見えた他の部分の羽も随分とボロボロになっていました。野鳥達にとって繁殖って大事業なんですね。
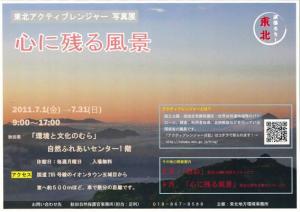
そして、森吉山野生鳥獣センターでは東北アクティブレンジャー写真展のスピンオフ企画、宮古アクティブレンジャー写真展『美しいこの光景は必ず復活します!!』を開催中です。過去3年間の宮古自然保護官事務所の高屋敷ARの写真を展示し、そこ場所の現在の情報を加えて展示してあります。
宮古を初め『被災した各地の、復興の道は果てしない』というイメージを持っている方が少なくはないようです。しかし現地では震災に影響を受けていないところもあります。例えば浄土ヶ浜VC前の駐車場から散策できる臼木山などはその一例です。また被災された皆さんが懸命に頑張って頑張って頑張って、観光客やハイカー達を迎える準備が整いつつあるところもあります。例えば浄土ヶ浜の観光船は今月16日に待望の再開を予定しているそうです。こうした現状を少しでも知っていただけたら!そして懸命に頑張っている観光地などへ足を運んで貰えるように!との思いを込めて開催しています。是非ご覧下さい。
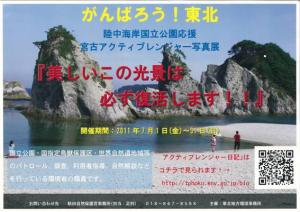
懸命に頑張っている姿というのはどうしてこんなにも心を打つのでしょうか?それは人間だけではなく先日、巡視の時に観察した【モズ】にも同じような感覚を持ちました。もしかしたら・・私は感傷的になっているかも知れません。。
森吉山麓高原内で多くの【モズ】達が繁殖中であることは以前この日記でもお伝えしました。現在はそれが佳境に入っていて、親鳥達が懸命に餌を運ぶ様子が観察できます。一日に何度運ぶのでしょうか?私が観察した時はオスもメスも入れ替わり立ち替わりで(概ね)5分と開けずに餌を運んできました。
オスの【モズ】がちょっと休憩(?)したところです。夕方になって疲労が蓄積していたのでしょうか?それとも日が暮れるまでもう一頑張りするためでしょうか?

よくみると・・・【モズ】の鮮やかなオレンジ色の羽がなりを潜め、灰色の地味な装いに替わっているではありませんか。巣のありかを周囲に悟られないようにヤブを潜って何度も何度も巣に餌を運んだからでしょうか?頭や背中部分の羽が擦り切れてきているようです。同一個体とは言い切れませんが同じ場所で数週間前に撮影した物と比べて、オレンジ色部分が無くなり灰色部分が拡大しているのが解りました。ストレッチしている時に見えた他の部分の羽も随分とボロボロになっていました。野鳥達にとって繁殖って大事業なんですね。
2011年07月04日月山山開き
磐梯朝日国立公園 羽黒 佐々木 大樹
7月1日に、月山山頂(月山神社本宮)で月山山開きが行われました。
月山には多くの登山口がありますが、今年は岩根沢登山口から入山して、清川行人小屋で前泊しました。
小屋では、朝日連峰保全協議会でいつもお世話になっている西川山岳会と皆様と一緒になりました^^

30日は展望があり、目指す月山が見えました。
しかし翌日の山開きの日は雨・・。本当に大雨で、久しぶりにこんなに雨に降られたという山でした。
平成23年は卯年ですが、月山神社では卯年を御縁年としています。
その卯年ということもあり、多くの参加者が安全祈願で参加されておりました。

清川行人小屋の近くでキヌガサソウを見つけました。
下りは姥沢ルートで下山しました。
岩根沢ルート、姥沢ルート共にまだ残雪がかなり残っています。悪天時は、地図とコンパスを使って進む必要があります。
特に岩根沢ルートは急斜面に雪渓が付いているので、登山を計画されている方はしっかり事前準備、情報収集をしてから入山するようにしてください。

姥沢の雪渓です。まだまだ残雪が多いです。
月山には多くの登山口がありますが、今年は岩根沢登山口から入山して、清川行人小屋で前泊しました。
小屋では、朝日連峰保全協議会でいつもお世話になっている西川山岳会と皆様と一緒になりました^^

30日は展望があり、目指す月山が見えました。
しかし翌日の山開きの日は雨・・。本当に大雨で、久しぶりにこんなに雨に降られたという山でした。
平成23年は卯年ですが、月山神社では卯年を御縁年としています。
その卯年ということもあり、多くの参加者が安全祈願で参加されておりました。

清川行人小屋の近くでキヌガサソウを見つけました。
下りは姥沢ルートで下山しました。
岩根沢ルート、姥沢ルート共にまだ残雪がかなり残っています。悪天時は、地図とコンパスを使って進む必要があります。
特に岩根沢ルートは急斜面に雪渓が付いているので、登山を計画されている方はしっかり事前準備、情報収集をしてから入山するようにしてください。

姥沢の雪渓です。まだまだ残雪が多いです。
2011年07月04日ヌマアジサシの仲間だった!
仙台 鎌田 和子
今日も、仙台はどんよりと重い雲がたれこめ蒸し暑い一日となりました。
6月中旬に伊豆沼のアジサシを紹介しましたが、双眼鏡を覗いて見た時も、写真でトリミングしてみても何だか自分の中で納得がいきませんでした。そこで調べてもらったり、自分でも調べてやっと、スッキリ!したので報告します。
鳥の種は「クロハラアジサシ」でした。その仲間はヌマアジサシ類と呼ばれ、コアジサシやアジサシと区別しているようで、ヌマは沼で、沼などの淡水域で多く見られるのでそのように呼ばれているようです。空中で昆虫類を捕ったり、水面すれすれを飛行して捕獲も可能、しかもちゃんとダイビングも!万能選手の感じかしら!

疑問に思ったのは、飛んでいる時の尾羽が短く、外側尾羽が長くない。

脚が赤い、頭の色、腹の斑模様など、確かに幼鳥・成鳥、冬羽根・夏羽根など紛らわしいのです。でもその中から情報を拾って、導かれて答えに辿りつくのですね。6月下旬には、このクロハラアジサシのほかに、ハジロクロハラアジサシも確認されたそうです。疑問に思うことは、勘違いや新しいことに出会うチャンスになればと、「日々是好日」「日々これ何?」でいきましょう!

「節電について」
東北地方環境事務所も本日から、LEDライトが導入され、手元の明かりで仕事に向かっています。職員それぞれが節電、省エネに努力、試行錯誤で頑張っています。
6月中旬に伊豆沼のアジサシを紹介しましたが、双眼鏡を覗いて見た時も、写真でトリミングしてみても何だか自分の中で納得がいきませんでした。そこで調べてもらったり、自分でも調べてやっと、スッキリ!したので報告します。
鳥の種は「クロハラアジサシ」でした。その仲間はヌマアジサシ類と呼ばれ、コアジサシやアジサシと区別しているようで、ヌマは沼で、沼などの淡水域で多く見られるのでそのように呼ばれているようです。空中で昆虫類を捕ったり、水面すれすれを飛行して捕獲も可能、しかもちゃんとダイビングも!万能選手の感じかしら!
疑問に思ったのは、飛んでいる時の尾羽が短く、外側尾羽が長くない。
脚が赤い、頭の色、腹の斑模様など、確かに幼鳥・成鳥、冬羽根・夏羽根など紛らわしいのです。でもその中から情報を拾って、導かれて答えに辿りつくのですね。6月下旬には、このクロハラアジサシのほかに、ハジロクロハラアジサシも確認されたそうです。疑問に思うことは、勘違いや新しいことに出会うチャンスになればと、「日々是好日」「日々これ何?」でいきましょう!
「節電について」
東北地方環境事務所も本日から、LEDライトが導入され、手元の明かりで仕事に向かっています。職員それぞれが節電、省エネに努力、試行錯誤で頑張っています。


昨日の白いサギから「白」繋がりで・・・今日は【シロキクラゲ】を取り上げました。
予定通りの巡視を終えて、戻ってくる途中で鳥獣保護区の管理員さんとバッタリ!!そこで情報交換して立ち話をしていましたが、話の流れで『じゃあ一緒に行こうよ』って事になって重い荷物を持ったまま別コースへ。
狙った成果は得られませんでしたが、今季初確認のトンボが見られたりとそれなりの成果があって、気をよくして「やっぱり歩く機会が多くなれば発見も多くなるもんだなぁ~」なんて思いました。この【シロキクラゲ】も気をよくした理由の一つ。こんな群生しているのは見たことがなかったので嬉しくなりました。
倒木にビッシリと【シロキクラゲ】が発生していました。写真の腕があればもう少し迫力が出せたかも知れませんが・・。
キクラゲはこれから先、群生するのを見る機会があるかも知れませんが【シロキクラゲ】は稀なはず!!
透き通るようで、瑞々しくて、触感もプルプル^^
やっぱり今年はキノコの当たり年かも知れませんね!!この他にもヒラタケの群生も見ましたし、ツルタケの仲間も大量に顔を出していました。歩道沿いに咲く花々が少々寂しい感じになってきましたが、キノコ観察はこれからが本番!!きっと楽しい観察が続くことでしょう。。
ところで・・・これをお読みになっている皆さんは『このキノコがどうなったのか?』気になっている方がいるようですね。
私が撮るのは写真だけ!!その場に残してあります。勿論鳥獣保護区管理員さんも持ち帰ることはありませんでした。なのでこの【シロキクラゲ】今も森吉山麓の何処かにあるんじゃないでしょうかね?ここに足を運ぶ人はまずいないでしょうから・・・。